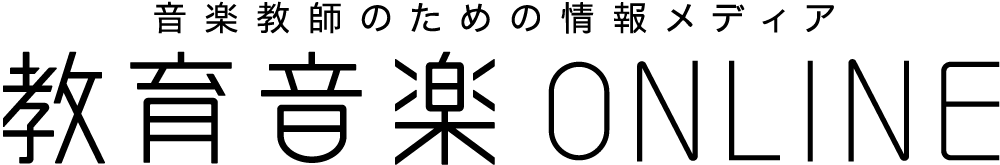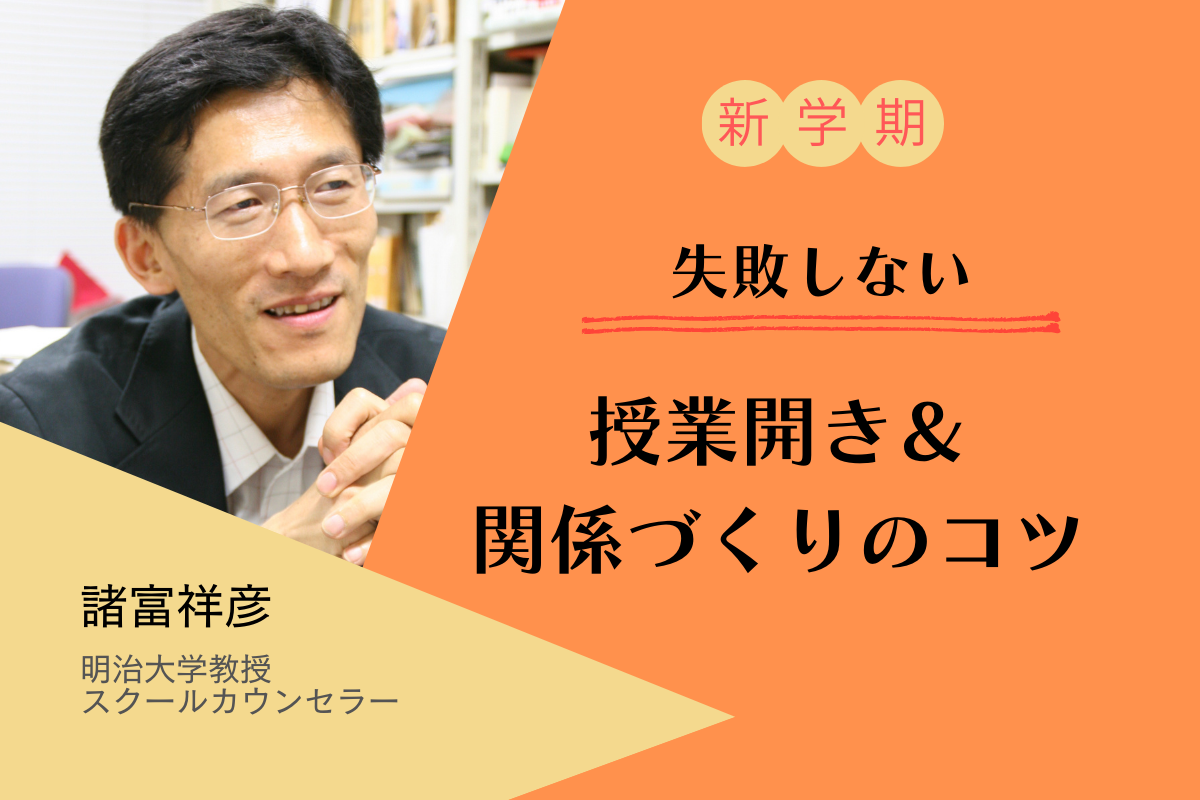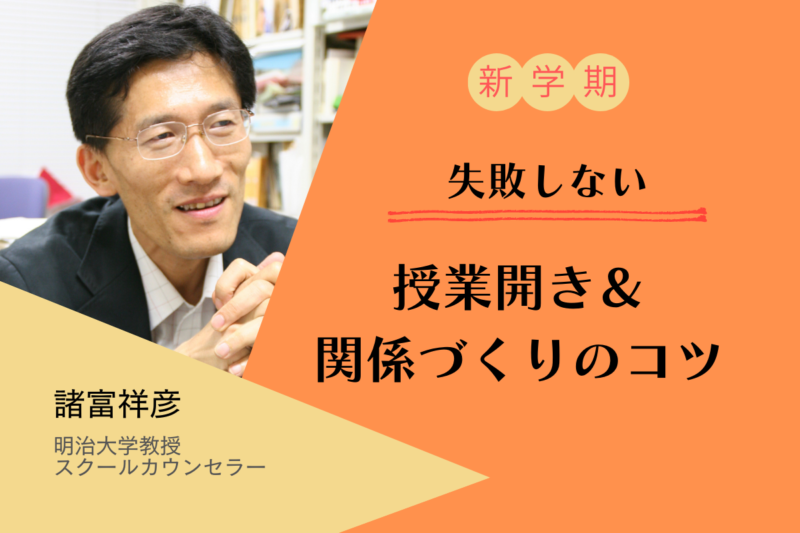
新年度、最初の授業で「何をするか」に意識が向いてしまうものですが、実は「何をしないか」が重要!? 1年間よい雰囲気で授業を行なっていくために、授業開きで気をつけることについて、スクールカウンセラーの諸富祥彦先生にお話を伺いました。
諸富祥彦(明治大学教授) 構成:長尾康子
●目次
初めての先生に出会う子どもの気持ちは?
自分の「発声」を意識する
連休明けまでに一人一人と直接話す
「何をするか」より「何をしないか」
アセスメントの視点を持つ
初めての先生に出会う子どもの気持ちは?
スクールカウンセラーという仕事柄、子どもたちの、先生や授業に対する気持ちを聞くことが多いのですが、音楽に限らず、どの教科でも、真面目で柔軟性のない先生ほど教科の内容をどんどん進めようとします。その様子が、「自分たちとの関係を大事にしていないようだ」と子どもが感じると、関係はつくりづらくなります。出会いの時点から、「子どもたちとの関係づくり」の視点を大事にする必要があるでしょう。
一般に、新しい先生に出会うのを子どもたちは楽しみにしています。今度はどんな先生なんだろう、とわくわくしています。ただし、小学校4年生以上になると、思春期の入り口にさしかかります。そういう子は、「どんな先生なんだろう。嫌な先生でなければいいな」と構えています。この場合、嫌な印象を与えるのを防ぐことが第一です。
子どもが嫌と思う理由はさまざまですが、大きな声で最初からどんどん進めてしまう、何かイラっとさせられるような先生は、子どもから見ると「ついていけない」という気持ちになります。そうした意味から、教師の第一印象はとても重要です。
落ち着いていて、イライラさせられない。ポジティブで、楽しさがある。これらの要素を最初に伝えることができたら、大成功ではないでしょうか。
自分の「発声」を意識する
具体的にはどうすればいいでしょうか。落ち着いた印象を与えるには、まず「声」がポイントになります。本人は意識していなくても甲高い、金切り声に近いようなカーッという声で突っ走るように話し続ける音楽の先生が時々います。先生自身は一生懸命やっているつもりでも、そんな声で話し続けられると、子どもたちは「疲れる」「やれやれ、先が思いやられるな」と感じてしまいます。
私もそうですが、話の内容に一生懸命になればなるほど、「自分がどんな声のトーンで話しているか、どんな印象を与えているか」に注意は向かなくなってしまうものです。人は、自分の盲点に気づきにくいのです。
これを防ぐには意図的に自分の「発声」に注意を向けるといいでしょう。気をつける、という意識ではなく、モニタリングする(自分で自分を観察する)のです。自分がどんな雰囲気で話しているか、「俯瞰する目」を持ちましょう。
自己紹介は意識的に「低めの声」で、速すぎない「ゆっくりとしたスピード」で話せば、落ち着きのある雰囲気が出せます。これだけでもずいぶん違うと思います。印象がよくなって、この先生は落ち着くな、と感じられます。張り切り過ぎると声にすぐ出てしまい、一人で舞い上がっている印象を与えます。この点は気をつけたいですね。