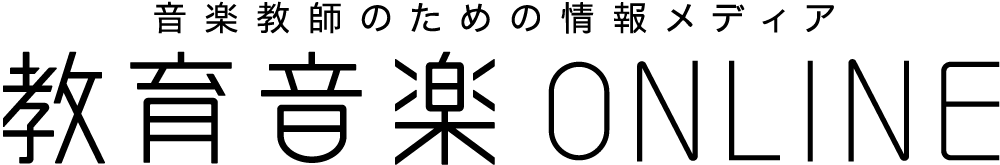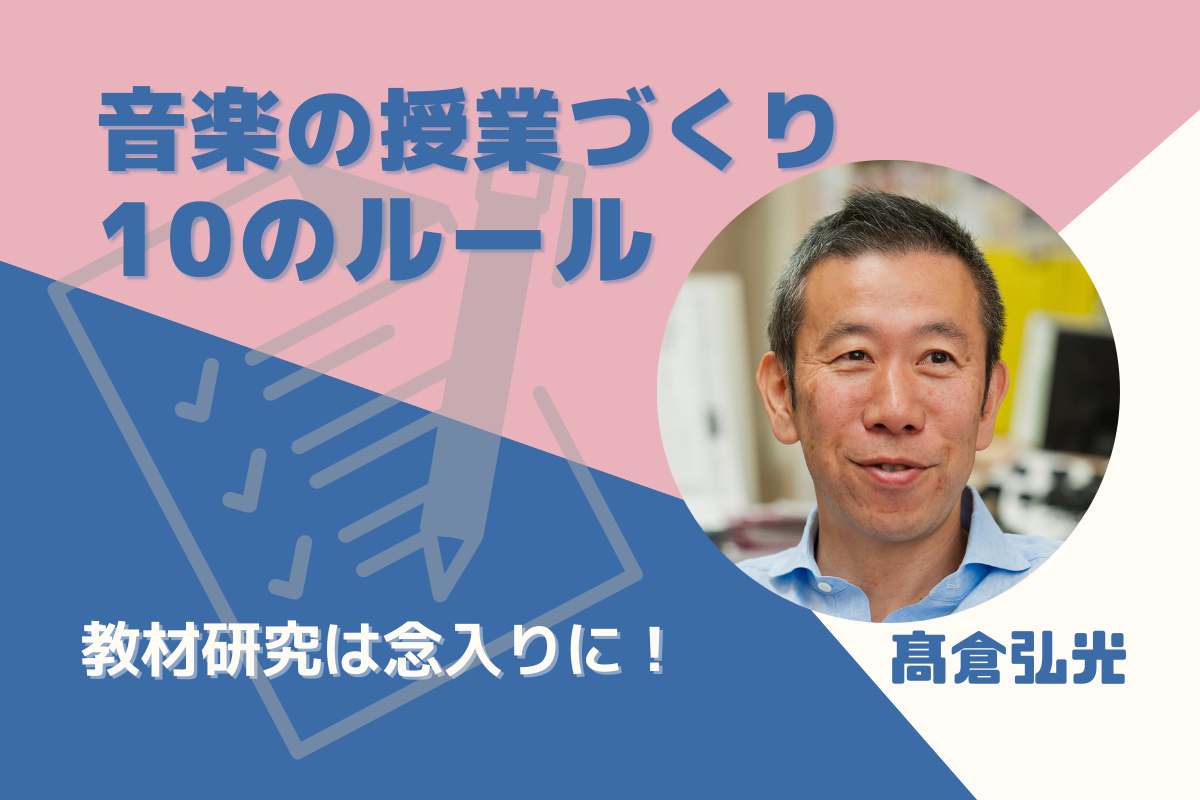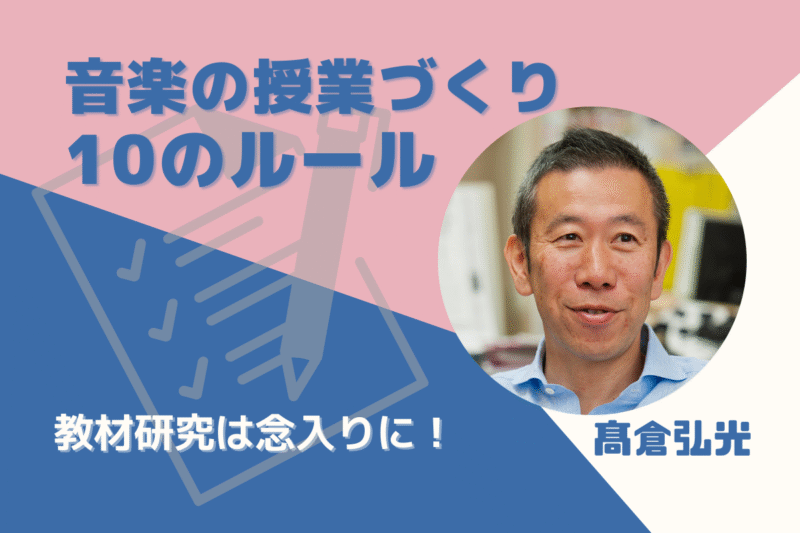
授業前にどのような準備をし、どのようなことを考えながら授業をしているか……。髙倉弘光先生が授業づくりで大切にしていることを紹介します。
髙倉弘光(筑波大学附属小学校副校長)
はじめに
「レッスン」でも「練習」でもなく、「授業」をどのようにつくるかという視点は、とても大切にしたいことです。私が考える授業づくりのルールは、大きく二つの側面があります。自分に課すルールと、子どもに対するものです。
私の10の授業ルール
授業前
ルール① 教材研究は念入りに
当たり前のことですが、授業の前には教材研究をします。たとえば歌唱の授業だったら、教材曲の分析をします。どのような旋律か、どのようなリズムが多いか、全体はどのような構成になっているか、それら歌詞との関係はどうか、自分なりに分析します。もちろん指導書などを参考にすることもあります。
ルール② 学習内容を明らかに
教材研究が終わったら、学習内容を明らかにします。教材研究で得たデータをもとに、対象となるクラスの子どもたちにフィットする学習内容を定めるのです。
たとえば、中学年の鑑賞授業で『白鳥』(サン=サーンス作曲)を取り上げるとき、私ならチェロとピアノの音色が重なり合って演奏されていることを聴き取ること、そして、チェロの旋律の優雅さを、白鳥というタイトルと関連づけて感じ取ることができること。この二つを学習内容と定めます。
これは、教材研究とは違い、次のステップ「授業研究」の段階になります。
ルール③ 授業の展開を考える
学習内容が決まったら、今度は実際にどのように授業を展開させるか、「学習活動」を考えます。『白鳥』の鑑賞でしたら、少なくとも二つの活動が大事になります。一つは、チェロとピアノの楽器の音色に気づかせるための活動、そしてもう一つは、チェロの旋律の優雅さに気づき、それを実感させるための活動です。私は、とくに後者の「優雅さ」を感じ取らせるために、体を動かす活動を効果的に取り入れたいと考えます。
ルール④ 「言葉」を定める
学習活動が定まったら、今度は授業の中で、実際にどのような言葉で子どもたちに「指示」するのか、あるいは「発問」するのかということを考えます。これはとても重要です。「発問の言葉」一つで授業がうまくいったり、いかなかったりします。成否に大きな影響を与えるのです。
だから、とくに研究授業などでは、一言一句、ノートに自分が話す文言を書き出しています。授業が始まって、何分くらいでこの展開、そしてこの発問を、この言葉で……という具合にです。普段はここまでやりませんが、この積み重ねがふだんの授業に生きるはずです。
ルール⑤ 展開をイメージする
ここまでで、授業の準備はほぼ終わりました。でももう一度授業を頭の中でイメージします。子どもたちの顔を思い浮かべながら。
「発問は考えたけれど、本当にあの子たちは自分の思った方向に考えを巡らせてくれるだろうか」と。一晩寝かせると「発問の文言を替えた方がいいな」と思い直すこともしばしばです。