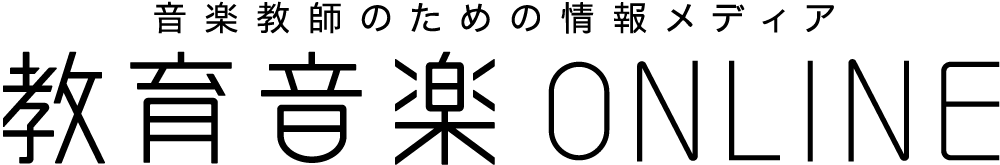日本ソルフェージュ研究協議会の新たなシリーズ「教育現場からの提言」の第1回「箏の古今」をリポート。「箏」に関する基礎知識、学校(小・中学校)や習い事における教育、邦楽のプロフェッショナルを目指す教育などについてレクチャーがなされた。講師は生田流の箏奏者である時松綾氏。氏は東京藝術大学にて、長年邦楽の学生向けのソルフェージュ授業も担当されている。会場となった講義室にはさまざまな大きさの箏が並べられ、壮観であった。
日本ソルフェージュ研究協議会主催
第1回 教育現場からの提言 ~箏の古今~
2025年2月1日 東京藝術大学5-109講義室
リポート:佐怒賀悦子(日本ソルフェージュ研究協議会理事)
写真:茂木道夫、編集部
「こと」の歴史
知られている日本最古の「こと」は、古墳時代の埴輪の弾琴像などに見られる。やがて和琴(わごん)へと進化していく。
5世紀になると、中国や朝鮮半島から雅楽が伝わり、楽器も演奏者も曲もセットで日本に伝えられた。芝さんや東儀さんは、ここから代々つながれてきた家系だそうだ。もともと我が国にあったものは和琴で奏され、「琴軋(ことさぎ)」と呼ばれるヘラ状のピックで弾く。雅楽の中ではもっとも位の高い者のみ奏することができる楽器だそうだ。会場にアルペジオで弾かれる和琴の太くおごそかな音(録音)が響き渡った。
さて、平安時代においては、「こと」は弦楽器全体の総称だったそうだ。次の4種類があった。
「琵琶のこと」
「箏(そう)のこと」:柱(じ)のあるタイプの「こと」
「琴(きん)のこと」:柱のないタイプの「こと」。印を指で押さえて音程を作る
「和琴」
源氏物語の「若菜下」巻に、紫の上は「和琴」を、明石の女御は「箏のこと」、明石の御方は「琵琶のこと」、女三宮は「琴のこと」を演奏するシーンが描かれている。その後雅楽は、宮中だけでなく寺院でも演奏されるようになり、江戸時代になると、「箏」だけが単独で演奏されるようになる。

時松 綾(ときまつ あや)
幼稚園で西洋音楽に触れ、5歳よりピアノを始める。ピアノ・楽典・ソルフェージュ等を大倉恭子に師事。ピアノを角野裕・榊原道子各氏に師事。東京藝術大学ソルフェージュ科非常勤講師。日本ソルフェージュ研究協議会会員。3歳より生田流箏曲、10歳より地歌(三味線)の手ほどきを祖母から受ける。東京藝術大学音楽学部邦楽科生田流専攻卒業、同大学院修了。NHK邦楽技能者育成会卒業。オーケストラアジアを経て現在邦楽創造集団オーラJ団員
箏の調弦法「平調子」
八橋検校は、今日の箏曲の基礎を築いた人物である。「検校」とは、目の見えない人たちによる組織の、最上級官位の名称。八橋検校が生み出した調弦法「平調子」は、雅楽の明るい音階に比べて暗い色調の音階であることが庶民受けして、広く普及していったそうだ。

前半は歴史や調弦法、楽譜など、箏にまつわる基礎知識について
さて、時松先生は、前もってチューナーを使って12平均律で調弦されている「平調子」の音階を弾いてくださり、続けて「六段の調」の冒頭を演奏された。その後「いつものとおりにしてみます」とおっしゃり、今度はご自分の耳で聴きながら柱の位置を微調整され、ふたたび音階を弾いて「先ほどの音階と比べてどうでしょう」と問いかけた。
「六段の調」の冒頭も演奏。後者の方がぐっと味わい深いように感じられた。後者の音階は、半音を12平均律の半音よりも少し(20セント*ぐらい)狭めたとのこと。ただし、半音をどれぐらいにするかは、曲目・流派・天気・体調等々によって変化するそうだ。
学校の教科書には、平調子が五線譜で書かれており、時松先生が現場に足を運ぶと、現場の先生方がチューナーを使って調弦し平均律のまま演奏している様子が見られるそうだ。「六段の調」などを演奏するときには、半音を少し狭くしたほうが落ち着きのある調べになる、ということを実演で示してくださった。
*セント:平均律の半音を100等分した、理論上の微分音程。半音は100セント、全音は200セントに相当。音響学者A.J.エリスによって提唱された音程表示の単位。
箏の楽譜のしくみ
そこで、いよいよ「六段の調」初段の楽譜(縦譜)を見ることに。記された漢数字はそれぞれの弦に充てられた名称で、遠い弦から「一二三四五六七八九十斗為巾」。数字の左に書かれている「テーントンシャン」などを西洋音楽のソルフェージュのドレミ唱のように歌う。箏は盲人の音楽だったので、楽譜は使わず「唱歌(しょうが)」で音楽が伝えられたのである。
同時に奏法もわかるようになっていて、たとえば、「テーントンシャン」の「シャン」は2本の弦を一緒にはじく、とか、数字の脇に書かれた「オ」は左手で押して一音上げる、「シュ」は素早くこすり風のような音を出す、「ツルツル」(すくい爪の連続)など。
昔の箏の稽古は毎日通うのが慣例で、先生が歌いながら、最初から少しずつ新しい部分を増やしつつ教えてくださり、それを身体で覚えていったのだそうだ。会場のみんなで「六段の調」の冒頭を歌ってみた。
生田流は、八橋検校の流れを汲んだ生田検校が創始した。一方、京阪神ばかりでなく江戸でも音楽を普及させようと山田検校などが立ち上がり、当時盛んだった浄瑠璃の影響を受けて、歌がメインの山田流箏曲が生まれたようだ。しかし現在、山田流が減少していることが危惧される、と時松先生は話された。

会場には箏がずらりと並べられた
伝統音楽・現代邦楽、それぞれの演奏・教授法・読譜
後半は、東京藝大の邦楽科箏曲専攻の学部生、大学院生、卒業生7名が加わり、実演を通してのワークショップとなった。
生田流の伝統音楽を専門とする4名は伝統譜だけを見て、一方現代箏曲を専門とする3名に時松先生が加わった4名は五線譜だけを見て、それぞれによって同一曲(『北国雪賦』長澤勝俊作曲)が演奏され、両者を聴き比べた。楽器編成は、第1箏、第2箏、十七絃箏、三味線(箏を極める人は必ず三味線も習得することが必須)。

後半は実演を交えて。伝統譜だけを見て演奏するグループと、五線譜だけを見て演奏するグループの演奏を聴き比べた
五線による合奏用のスコアでは、和音の響きやメロディーの受け渡しが図形的に見える。それに対して伝統的な縦譜は、いわゆるタブラチュア譜(どの弦を弾くかを示す)なので、楽器の違い、またその時々の調弦の変化によって、他の楽器が何をやっているのかを掴むのは困難のようだ。
その代わり、伝統譜には縦譜の作成者による指使いが書いてあり、それが個々の演奏表現につながるようだ。また、西洋のソルフェージュでは、基本的にはまず楽譜に忠実に演奏することを学ぶが、伝統譜で古典を習う場合は、先生を真似て唱歌を口ずさみながら、テンポの取り方やリズムの捉え方も含め、伝統的な表現様式を吸収し継承していく、というところが大きな違いのようだ。
五線に書かれた現代邦楽――和や洋のエッセンスが見え隠れする楽曲を演奏する場合は、洋に寄り過ぎると箏で演奏した意味がなくなってしまうため、どの程度にするのが適切なのかを考えるのだそうだ。そのために西洋の五線の読譜方法も学びつつ、箏の伝統的な様式をしっかり身体に入れることも大切。頭の中で歌う際にも、ドレミで感じたり、唱歌で感じたりを場面に応じて使い分ける、と伺い、たいへん興味深く感じた。

西洋音楽と日本音楽が融合した現代邦楽。伝統的な様式と西洋音楽の観点を交えながら演奏しているという
ヴァイオリンの鈴木メソード創始者の鈴木鎮一先生の父君は、ヴァイオリン制作を始める前は和楽器商で、長唄の素養があった、という納得のエピソードや、さまざまな多絃箏に関する話の中で、宮城道雄が「八十絃」を作ったという驚くような話題など、興味が尽きなかった。
ところで、箏曲の演奏家の減少により、大手の箏の楽譜出版社や、糸(テトロン)製造メーカーの廃業など、事態は深刻のようだ。継承者の減少にも危機感を覚えているとのお話。学校教育なども通して、子どもたちがよりすてきな演奏に触れる機会を設け、興味を広げられるように、流派を超えた子どもの初動教育の環境を作っていくことが課題である、と話された。
今回の「提言」では、私自身新しく知ることも多く大いに触発された。ぜひ、日本の伝統楽器の素晴らしさ奥深さが見直され、後世に継承していく環境や仕組みが作られることを期待したい。
最後に、「箏曲」の「こと」は「箏」の字を用いること。「琴」の字は、主に大正琴、一弦琴や「柱」のない「こと」に使う(例外として和琴には柱がある)。また「筝」の字は略字なので用いないこと、とのご助言があった。ぜひ覚えておきたい。